今日泣いている誰かが、明日「生まれてきてよかった」と思えるような社会であってほしい。
このような“祈り“を込めて、社会起業家たちの支援を行う会社がある。
関西を中心に社会起業家への育成や投資、企業と起業家に対するオープンイノベーション支援などを行っている株式会社talikiだ。
前編では、社会課題解決領域における「社会に向き合い、行動する個への支援のあり方」について焦点を当てた。
今回の後編では、taliki創業者である中村多伽氏の人生や、そこから見えた「社会起業家に共通するもの」、「社会に向き合うために必要なこと」について答えていただいた。
特集0:「SOCIAL QUANTUMS make another now to happen. 社会の小さな担い手が、新たな“当たり前”を創り出す」
今回の特集では、anowと同じく社会を担うために奮闘する“個”を支援する人や組織、コミュニティ、また彼らの存在の意義や定義を考える研究者へのインタビューを通じて、SOCIAL QUANTUMSのあり方や、彼らが活躍していくための条件・要素を深掘り、anowが描く”個と社会の理想的な姿”の糸口を探る。

PROFILE

中村 多伽
株式会社taliki
代表取締役CEO / talikiファンド代表パートナー
1995年生まれ、京都大学卒。カンボジアに2校の学校建設を行った後、ニューヨークへ留学。現地報道局に勤務し2016年大統領選や国連総会の取材に携わる。様々な経験を通して「社会課題を解決するプレイヤーの支援」の必要性を感じ、帰国後に株式会社talikiを設立。社会起業家のインキュベーションや上場企業の事業開発を行いながら、2020年には国内最年少の女性GPとして社会課題解決型ベンチャーキャピタルを設立し投資活動にも従事。
「わたしは生まれてきてよかったのか?」からはじまった社会への視線
talikiの創業には、中村氏が大学時代に経験したカンボジアでの小学校建設にまつわる社会の構造的課題への気づきや、ニューヨークで経験した「組織の大きさではなく、プレイヤーの絶対数」という学びといったきっかけがあった。
しかし、そのような社会課題に対する視点はどのように中村氏に芽生えたのだろうか。
中村氏曰く、それは「自分が生まれたことへの疑問」から始まったという。

中村氏は、「自分自身の“生きるという選択“を続けたことが、誰かの幸せに少なからずつながった」ということが、そこからのtalikiを通じた“誰かの課題の手助け”というアプローチに結び付いていると話す。
幼少期から青年期にかけてのこのような体験・感情からtalikiが生まれているということは、talikiの支援先である社会起業家の“共通点“にも反映されている。
”痛み”という、個人が社会に向き合うスイッチ
中村氏は、社会課題に向き合い、何かしらの変化を起こそうとする人には、「深い痛みを経験している」という共通点があると指摘する。
 talikiでは、様々な課題意識を持つ社会起業家候補たちが集まり、解決のアイデアを磨いている。
talikiでは、様々な課題意識を持つ社会起業家候補たちが集まり、解決のアイデアを磨いている。
そこで、talikiでは「課題に対して、解像度を高く認識している」という点を重視し、社会起業家への支援を決定している。
これは、課題の解像度が高い=深い痛みを持った上で解決に向けたエネルギーを持っている、と中村氏が考えているからだ。
当然、「痛みの経験を持つ」ということが、誰かに対する社会的・個人的暴力を肯定するものとして解釈されることは、絶対に避けられるべきことであり、ここで述べている“痛み”とは、それらと同義ではない。
社会に生きる中で、どうしても体験してしまい、負ってしまった“つらい体験”や“悲しみ”といったものを、「これ以上、同じことが起きないように」という祈りを込めて、社会を変える力に転換しようとする人々が、talikiの支援したい存在であり、かつtalikiに集まる起業家たちの共通点である。
しかし、全ての人が“痛み“の経験を受け止め、それを社会課題解決に向けるようになれるわけではないことも、私たちは知っている。
では、人々が“痛み”を“誰かのための力”に変えていくために必要なものとは何なのだろうか?
痛みが痛みで終わらないような”出会いのデザイン”を
誰しも、日常を生きる中で多かれ少なかれ“痛み”を感じて生きている。
家族関係や友人関係といったものから、社会的冷遇や世の中の構造の皺寄せなど、それらは多岐にわたるため、一概に同じような“痛み”として考えることは難しい。
しかし、そのような多様な“痛み”を経験しながらも、それを“力”へと変換し、誰かのために使おうとするのが社会起業家の共通点なのではないか。
そこで、中村氏に「『痛み』が『力』に転換し、誰かの課題解決に向かうには何が必要なのか?」という問いかけをしてみた。

talikiと出会うことで、起業家になる前の個人が自分自身の“痛み”に向き合い、それが他者・社会に存在する“痛み”と繋がっているということを感じられるからこそ、そこから社会を変えていこうというエネルギーが生まれる。
talikiの取り組みに限らず、様々な場面で“出会いのデザイン“をすることで、少しづつ「“痛み“を“痛み“で終わらせない仕組みづくり」に取り組んでいけるといえるのではないだろうか。
「関与人数を増やす」という一つの希望
“痛み”を“誰かのための力”に変え、社会課題解決に繋げていくことが、talikiの取り組んでいる支援の根幹にあるものだが、全ての人が社会課題解決を牽引する存在になることを描いているわけではないと、中村氏は強く言及する。

また、直接的に社会解決目的の企業や取り組みに参加するといった形だけじゃなく、「間接的な関与のあり方に対しての模索が重要である」と、中村氏は言う。
自分の身の回りの課題や苦しさに気づきながらも、関与のレベルが高いことでなかなか動き出せない人は当然存在する。
だからこそ、間接的にも関与を行っていくことが、社会課題を解決する“誰かのための力”になれるという中村氏の言葉は、多くの人々にとって勇気を与える。
この記事を読んでくれた読者の中で、これまでに“痛み”を抱えて生ていた経験があったり、現在進行形で“痛み”に苛まれている人がいるならば、まず「小さな関与から始める」という“はじめの一歩“を踏み出してみるのはどうだろうか。
それだけのことでも、大きなエネルギーが必要で、自分自身の“痛み”に向き合うことのつらさがあるかもしれない。
だが、その小さな関与を手にすることが、あなた自身の“痛み”を“誰かのための力”に変えていける、希望に満ちた出会いになるかもしれないと、筆者は信じたい。
talikiの挑戦の一部を垣間見た立場だからこそ、そのように読者へ伝えたいと素直に思うのだ。
取材場所協力:engawa Kyoto
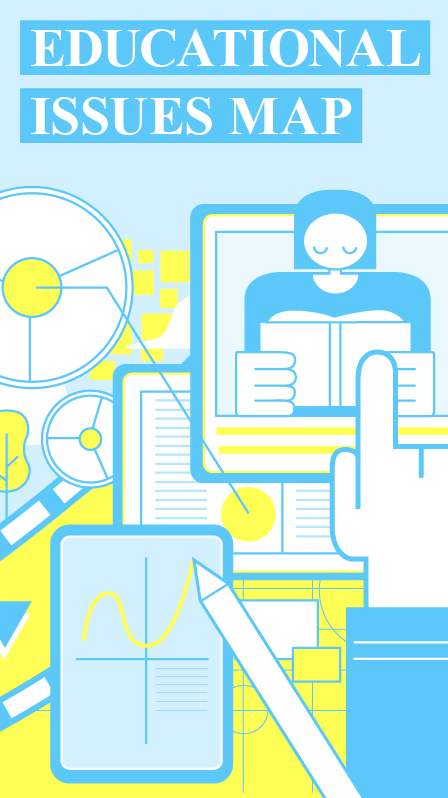



















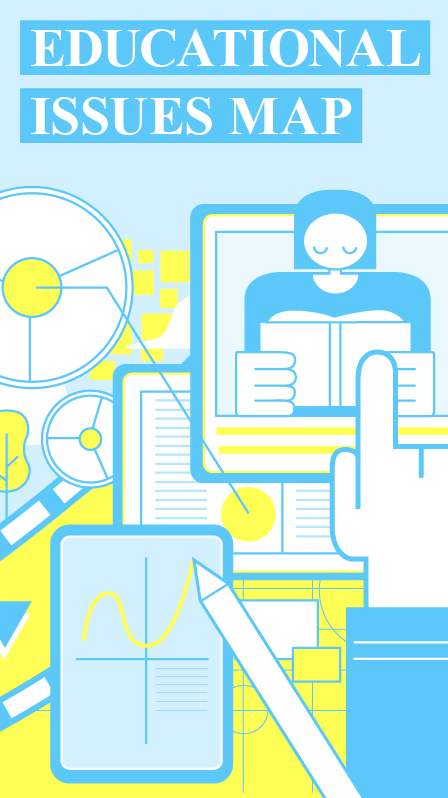
















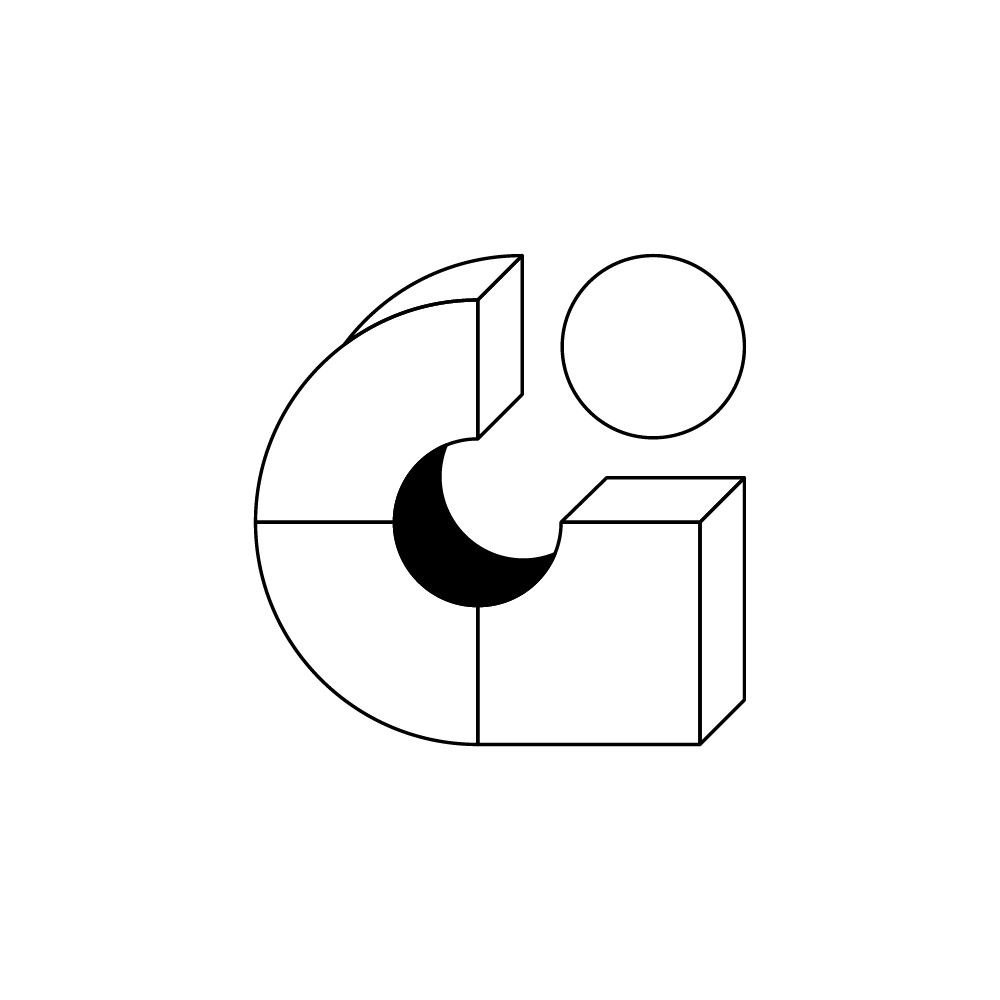









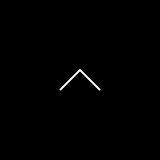
中村:もともと、一見順風満帆のように見えて、実はすごく綻びがあるような環境で育ったという背景がありまして。
いろいろな部分から、「自分が生きてる理由ってなんだろう?」と思うような幼少期〜青少年期を過ごしてきたんです。
その中、カンボジアで小学校を建てたことをきっかけに、少なくとも誰かの人生が一時的に好転するという経験ができて、自分が生きてきたからこそ、誰かの幸福に携われる瞬間に立ち会えたんだなと思ったんです。
社会の理不尽によって、苦しんでいる人がいたり、自分の責任ではないところで命を失う人に対して自分の命を使うことが、生きてる理由になるのではないかと、そこから真剣に考えるようになりました。